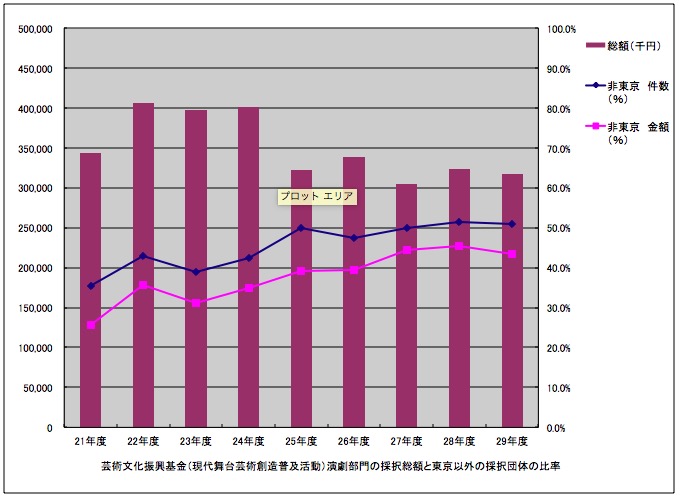●分割掲載です。初めての方は(予告)から順にご覧ください。
新しいジャンルの表現に触れてみたいと思ったとき、私が最も参考にするのは信頼出来る友人知人の推薦です。自分の感性に近いと思える人はわかっていますので、その人が強く薦めるものなら、自分が普段接していないジャンルでも、足を運んでみようという気になります。Twitterも同じ使い方をしており、アンテナ代わりにさせていただいている方が何人かいて、その方が薦めることで観たものがたくさんあります。著名人による推薦は気になる場合もありますが、その著名人の仕事に惚れ込んでいない限り、それほど影響は受けません。やはり相手の人となりを知り、感性を理解していることが重要だと思います。