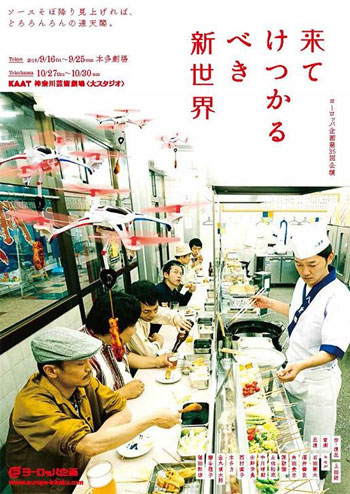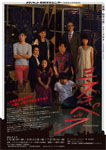久しぶりに日本劇団協議会機関誌『join』88号特集「私が選ぶベストワン2016」に参加させていただいた。今回から発行時期が早まり、例年の3月末から2月末になるそうだ。
作成者別アーカイブ: 荻野達也
演劇の創客について考える/(16)2015年の演劇公演回数は横ばいながら市場規模は大きな伸び
演劇の創客について考える/(15)チラシの必要性とチラシ束の必要性を明確に区別して考えよう
上演中スマートフォンの「機内モード」を認めることに異議あり、なぜ「電源は必ずお切りください」にしないのか
上演中は携帯電話・スマートフォンなど、音の出る機器を電源から切るようお願いするのが一般的だが、小劇場で最近「電源から切るか、機内モードにしていただくよう」というアナウンスを聞くようになった。私の場合、今年に入って3公演で遭遇した。
私がいま旗揚げカンパニーのチラシをつくるとしたらB5判でつくる。そのほうがA4判だらけのチラシ束で印象に残るから
舞台芸術のチラシは、1990年代前半まで映画と同じB5判が主流だった。A4判化が急激に進んだのは93年からで、A4判が多くなってくるとB5判が目立たなくなってしまい、現在ではA4判のほうが一般的になった。昔からのフォーマットを崩したくない一部カンパニーだけがB5判を続けている状態だ。
演劇の創客について考える/(14)「日本一の文化祭」都立国立高校「国高祭」のクラス演劇が教えてくれること
●分割掲載です。初めての方は(予告)から順にご覧ください。
高校の文化祭シーズンですが、全国にはクラス演劇の競演で有名なところがあります。東京だと都立青山高校「外苑祭」、都立日比谷高校「星陵祭」、東京学芸大学附属高校「辛夷祭」などが有名ですが、中でも3年各クラスによる演劇で「日本一の文化祭」と言われるのが、都立国立高校「国高祭」です。
演劇の創客について考える/(13)書店の在り方を一から考え直す『これからの本屋』、演劇の世界に通じる発想だらけ
●分割掲載です。初めての方は(予告)から順にご覧ください。
本が売れなくなっています。書店自体もネット書店に押され、リアル書店は激減しています。出版科学研究所(公益社団法人全国出版協会)の調査によると、2015年の紙の出版物の推定販売額前年比は、1950年の調査開始以来最大の減少率5.3%で、850億円が失われた計算になります。これはジュンク堂や有隣堂クラスの大型チェーンが2社潰れたのと同じ規模だそうです。全国の自治体の17%が「書店ゼロ」だそうです。
演劇の創客について考える/(12)2013年を契機に小劇場の集客は増加傾向にある
「事前精算限定のチケット販売システム」アンケート結果を見て考えたこと――当日精算の連絡なしキャンセルが10%いるのなら、ソーシャルチケットサービスの手数料相場5%のほうが安い
決済機能を持ったチケット販売システムを検討するため、3月に有限会社レトロインク(東京都三鷹市)がオンラインアンケートを実施した。2週間で118名から回答があり、集計結果を基に関係者が意見交換を重ねたが、次の2テーマに解決策が見出せなかったため、当面はシステムの製作を見合わせることを6月16日発表した。
宮崎県立芸術劇場は『三文オペラ』上演を宣言する前にもっと検証すべきことがあるのではないか、なぜ「演劇ディレクター」と情報共有しなかったのか
公益財団法人宮崎県立芸術劇場が企画制作する「演劇・時空の旅」シリーズ#8『三文オペラ』(作/ベルトルト・ブレヒト、演出/永山智行)が初日開場後に公演中止した問題について、株式会社酒井著作権事務所(旧・オリオン)に質問状を送っていた劇場側が、その後の方針を6月19日に公表した。「近い将来、改めて『三文オペラ』を上演する」と宣言している。