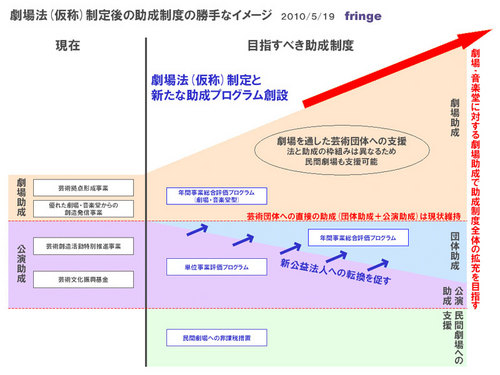座・高円寺が3月27日~28日に開催した子供向けワークショップの発表会タイトルが、「飛ぶ劇場」となっている。演劇界で「飛ぶ劇場」と言えば、当然ながら北九州のカンパニー・飛ぶ劇場を思い浮かべるわけで、私もこのタイトルを最初目にしたときは、「こんな時期に飛ぶ劇場の東京公演ってあったっけ」と戸惑った。飛ぶ劇場主宰の泊篤志氏も東京の友人から連絡を受けて驚き、個人ブログでこう書いている。
ハッキリ言ってー、そのー、ちょっとコレは紛らわしいなぁー
んー
勘違いする人、他にも居るんじゃないかなぁ。
「飛ぶ劇場」というネーミングは確かにありがちで、小劇場に詳しくない人なら使ってしまうかも知れない。このワークショップも外部のアートNPOに運営を委託しているようで、彼らが北九州の飛ぶ劇場を知らなかったのかも知れない。けれど、このタイトルを見た座・高円寺の学芸スタッフや広報スタッフは当然小劇場の専門家のはずだから、その時点で変えるようアドバイス出来たのではないだろうか。
商標登録されている名称ではないので、使っていけないということはない。演劇以外のジャンルなら、勘違いする人もいないだろう。しかし、座・高円寺という小劇場演劇を軸にした専門劇場で「飛ぶ劇場」を使ってしまうのは、いくら学芸事業でも配慮に欠けるのではないだろうか。誤解を招くこともそうだが、この名前を長年使っているカンパニーに対するリスペクトを持ってほしいと思う。「鳥の劇場」も同じ理由で使えないと思う。
(2010年3月31日追記)
本記事掲載直後、座・高円寺広報より連絡をいただいた。
飛ぶ劇場の存在は承知していたが、ケストナーの『飛ぶ教室』を強く意識した佐藤信芸術監督の要望により、敢えて事業名として使用したという。ただし、カンパニー側にその旨を伝えていなかったのは軽率であり、カンパニー側に早急に連絡を取ってお詫びするとのこと。
3月30日付のブログトマリ「続報、『偽の飛ぶ劇、東京に現る?』」によると、劇場から連絡があり、この名称は今後も使用したいが、同一表記を避けるため、「とぶげきじょう」のようなひらがな表記を考えていきたいという。