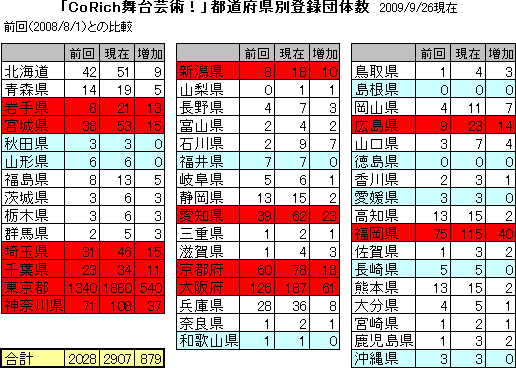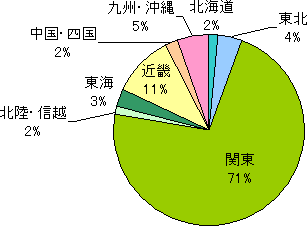アーティクルのタイトルは帯の惹句から。手掛けた舞台52本がすべて黒字という、シス・カンパニーの北村明子プロデューサーによる新書。
ご本人が直接書いたのではなく、『アエラ』の名物ルポ「現代の肖像」で北村氏を担当した島崎今日子氏の取材・文による「語りおろし」。それら過去記事を読んでいれば重複する個所も多く、特に目新しさはないが、彼女を知らない読者がそのポリシーや軌跡を追うにはいいだろう。
巻末には、こまつ座との共同プロデュース『ロマンス』(2007年)で北村氏の仕事を間近で見た井上ひさし氏の文章とプロデュース全作品リスト。サブタイトルは「『好き』をビジネスに変えたプロデューサーの仕事力」。
(参考)
「現代の肖像」北村明子氏
小学館
売り上げランキング: 8573